近年、不動産業の事業譲渡に関するご相談が増えています。中でもよくいただくのが、
「不動産部門の譲渡を受けたら、相手の宅建免許も引き継げるの?」という質問です。
この記事では、事業譲渡における宅建免許の取扱いについて、実際のQ&A形式を交えてわかりやすく解説し、免許取得の注意点やスケジュール管理の重要性についても触れていきます。

事業譲渡と宅建業免許:基本原則
宅建業免許は譲渡できない
宅建業免許は、その性質上、事業譲渡によって自動的に譲渡・承継されるものではありません。譲渡会社(譲渡元)の免許は、事業譲渡後には効力を失います。宅建業法は、個々の事業者の資質や能力を評価して免許を与える制度であり、その免許は特定の事業者に紐づいています。したがって、事業譲渡という形をとっても、免許そのものが自動的に譲渡先に移転することはないのです。この原則を理解しておくことは、事業譲渡を検討する上で非常に重要です。事業譲渡を行う際には、この点を十分に考慮し、適切な対応策を講じる必要があります。免許の譲渡が不可能である以上、譲受会社は自ら新たな免許を取得しなければなりません。この点を軽視すると、事業の継続に支障をきたす可能性があります。
◼ Q&Aで確認!
Q:宅建免許を持っていないA社が、宅建免許を持っているB社の不動産事業を譲り受けた場合、A社の宅建免許も引き継げますか?
→ A:引き継げません。A社が自ら新規に宅建免許を取得する必要があります。
これは法人格が異なる以上、どれだけ業務を引き継ごうとも「免許」は譲渡対象にはならないためです。
譲受会社は新規に免許取得が必要
事業を譲り受ける会社(譲受会社)が引き続き宅建業を行うためには、新たに宅建業免許を取得する必要があります。このプロセスは、通常の新規免許申請と同様の手続きとなります。譲受会社は、免許取得のための要件を満たし、必要な書類を準備し、申請を行う必要があります。免許の申請から取得までには一定の期間を要するため、事業譲渡のスケジュールに合わせて早めに準備を進めることが重要です。また、免許取得の際には、事務所の所在地や規模、人的構成など、様々な要件が審査されます。これらの要件を満たしていることを確認し、不備がないように申請を行う必要があります。免許取得の遅れは、事業の開始時期に影響を与える可能性があるため、綿密な計画と準備が不可欠です。
事業譲渡における宅建免許の取り扱いポイント
- 事業譲渡により宅建業の業務を引き継いでも、免許自体は引き継げない
- 免許がない会社(A社)が不動産業を継続するには、新たに免許を取得する必要がある
- 免許取得には一定の期間と準備が必要。事業開始時期に影響する可能性もある
- 保証協会加入や営業保証金の供託も、新たに手続きが必要
免許取得の条件
宅建業免許の取得には、人的要件(宅地建物取引士の設置など)、財産的要件、事務所要件など、一定の条件を満たす必要があります。譲受会社はこれらの要件をクリアする必要があります。人的要件としては、宅地建物取引士の設置が義務付けられています。事務所要件としては、事務所が独立性を有し、適切な広さや設備を備えている必要があります。財産的要件としては、一定額以上の資本金や自己資金を有している必要があります。これらの要件は、宅建業法によって定められており、厳格に審査されます。譲受会社は、これらの要件を事前に確認し、必要な準備を行う必要があります。要件を満たしていない場合、免許の取得が認められない可能性があるため、注意が必要です。また、これらの要件は、都道府県によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
事業譲渡における宅建免許取得の手続き
宅建業免許の取得は、書類の準備から免許交付まで時間がかかるため、事業譲渡のタイミングとの調整が非常に重要です。

【免許取得の流れ】
① 免許申請準備
② 保証協会への加入申込み(または営業保証金の供託準備)
③ 行政庁による審査
④ 保証協会の審査・分担金納付(or保証金の供託)
⑤ 免許証交付
【標準処理期間の目安】
- 都道府県知事免許(単一都道府県内):約30〜40日
- 国土交通大臣免許(複数都道府県にまたがる場合):約3ヶ月
- 保証協会加入:約2ヶ月
このスケジュールを見ても、最短でも約2〜3ヶ月前には準備開始が必要になります。
事前準備の重要性
事業譲渡の計画段階から、宅建業免許の取得スケジュールを考慮に入れることが重要です。免許取得には時間がかかる場合があるため、事業譲渡の時期と免許取得のタイミングを調整する必要があります。具体的には、免許申請に必要な書類の準備、事務所の確保、宅地建物取引士の確保などを、事業譲渡のスケジュールに合わせて進める必要があります。免許取得の遅れは、事業の開始時期に影響を与えるだけでなく、顧客からの信頼を損なう可能性もあります。そのため、事業譲渡の計画段階から、免許取得のスケジュールを詳細に検討し、綿密な準備を行うことが不可欠です。また、免許取得の際には、様々な審査が行われるため、事前に専門家(行政書士など)に相談し、アドバイスを受けることも有効です。
必要書類の準備
宅建業免許の申請には、多くの書類が必要となります。法人の場合は、会社の登記簿謄本、役員の履歴書、事務所の写真などが挙げられます。個人の場合は、住民票、身分証明書などが必要となります。これらの書類は、申請の種類や都道府県によって異なる場合があります。そのため、事前に申請先の窓口に確認し、必要な書類を正確に把握しておくことが重要です。また、書類によっては、取得に時間がかかるものもあるため、早めに準備を始める必要があります。不備のある書類を提出すると、申請が受理されない場合があるため、注意が必要です。特に、役員の履歴書や身分証明書などは、正確な情報を記載する必要があります。書類の準備は、免許取得のプロセスにおいて非常に重要なステップであるため、慎重に進める必要があります。
営業保証金の供託または保証協会への加入
宅建業免許を取得するためには、営業保証金を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入する必要があります。保証協会への加入には、分担金の納付が必要です。営業保証金の供託は、顧客の損害を担保するための制度であり、一定額の金銭を法務局に預ける必要があります。一方、宅地建物取引業保証協会への加入は、営業保証金の供託に代わるものであり、協会が顧客の損害を保証する制度です。保証協会への加入には、入会金や分担金の納付が必要となりますが、営業保証金を供託するよりも負担が少ない場合があります。どちらを選択するかは、会社の規模や資金状況などを考慮して決定する必要があります。また、保証協会への加入には、協会の審査が必要となるため、事前に準備を進める必要があります。
事業譲渡と免許番号の変更
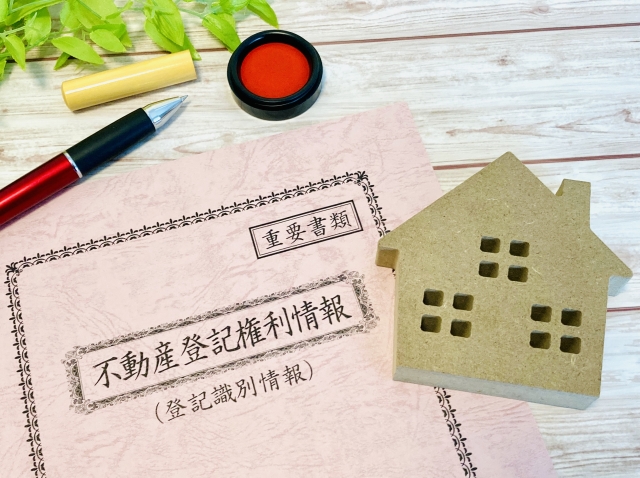
免許番号の重要性
宅建業免許の番号は、不動産業者の信用度を示す指標の一つです。事業譲渡により免許番号が変わることは、顧客への告知が必要となる場合があります。免許番号は、不動産業者が過去にどのような業務を行ってきたか、どのような実績があるかを示す情報として、顧客に認識されています。そのため、免許番号が変わることは、顧客に不安感を与える可能性があります。事業譲渡の際には、免許番号が変わる理由を顧客に丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。また、新しい免許番号を取得した後も、引き続き質の高いサービスを提供し、顧客からの信頼を維持することが重要です。免許番号は、あくまで指標の一つであり、サービスの質や実績が最も重要であることを忘れてはなりません。
免許番号変更の影響
免許番号が変わることで、過去の実績や顧客からの信頼がリセットされる可能性があります。事業譲渡の際には、この点も考慮に入れる必要があります。免許番号が変わることは、過去の実績や顧客からの信頼が完全に失われるわけではありませんが、顧客によっては、新しい業者として認識される可能性があります。そのため、事業譲渡後も、積極的に顧客とのコミュニケーションを図り、信頼関係を再構築する必要があります。また、過去の実績をアピールする際には、事業譲渡の経緯を説明し、誤解を招かないように注意する必要があります。免許番号が変わることは、デメリットだけでなく、新しいスタートを切るチャンスでもあります。事業譲渡を機に、サービスの質を向上させ、顧客満足度を高めることで、信頼を回復することができます。
顧客への丁寧な説明
事業譲渡後もスムーズに事業を継続するためには、顧客に対して事業譲渡の経緯や今後のサービスについて丁寧に説明することが重要です。免許番号の変更についても、理解を得られるように努めましょう。顧客は、事業譲渡によってサービスの内容が変わるのではないか、品質が低下するのではないかといった不安を抱いている可能性があります。そのため、事業譲渡の目的や、今後のサービスについて、丁寧に説明する必要があります。また、免許番号の変更についても、理由を明確に説明し、顧客の理解を得るように努めましょう。顧客への説明は、対面で行うだけでなく、書面やメールなど、様々な方法で行うことができます。顧客が安心してサービスを利用できるよう、丁寧な説明を心がけましょう。説明会などを実施することも有効な手段です。
不動産会社倒産と事業譲渡

倒産手続きにおける事業譲渡
不動産会社が倒産する場合、M&Aの一つの手段として事業譲渡が選択されることがあります。この場合も、譲受会社は新たに宅建業免許を取得する必要があります。倒産手続きにおける事業譲渡は、債権者への弁済資金を確保する手段として利用されることがあります。譲受会社は、倒産した不動産会社の事業を引き継ぎ、事業を継続することで、顧客へのサービス提供を維持することができます。ただし、譲受会社は、倒産した不動産会社の債務を引き継ぐわけではありません。譲受会社は、新たに宅建業免許を取得し、自社の責任において事業を行う必要があります。倒産手続きにおける事業譲渡は、複雑な法的手続きを伴うため、専門家(弁護士など)に相談することが不可欠です。事業譲渡の手続きを適切に進めることで、債権者への弁済を最大化し、事業の継続を図ることができます。
顧客との契約関係
不動産会社が倒産した場合、顧客との契約関係がどうなるかが問題となります。事業譲渡によって契約が引き継がれる場合もありますが、個別の契約内容によって異なります。一般的に、事業譲渡によって契約が自動的に引き継がれるわけではありません。譲受会社が契約を引き継ぐためには、顧客の同意が必要となります。顧客は、事業譲渡によって契約内容が変わるのではないか、履行が確実に行われるのかといった不安を抱いている可能性があります。そのため、譲受会社は、顧客に対して契約の引き継ぎについて丁寧に説明し、同意を得るように努めましょう。契約の引き継ぎには、書面による合意が必要となる場合があります。また、契約内容によっては、事業譲渡によって契約が解除される場合もあります。
弁護士への相談
不動産会社の倒産手続きは複雑であるため、弁護士に相談することをおすすめします。事業譲渡の可能性や、顧客との契約関係について、適切なアドバイスを受けることができます。倒産手続きは、法律や税務に関する専門的な知識が必要となるため、弁護士や税理士などの専門家に相談することが不可欠です。
弁護士は、事業譲渡の可能性を検討し、最適な方法を提案してくれます。また、顧客との契約関係について、法的な観点からアドバイスをしてくれます。弁護士は、債権者との交渉や、裁判所への手続きなども代行してくれます。弁護士に相談することで、倒産手続きをスムーズに進め、債権者への弁済を最大化することができます。また、事業の継続に向けた道筋をつけることができます。弁護士への相談は、早期に行うことが重要です。
宅建業免許の名義変更が必要なケースとして「会社分割」や「組織再編」にも注意
近年、「組織再編」や「グループ再編」による宅建業の承継や引き継ぎのご相談が増えています。特に「会社分割」(新設分割・吸収分割)を活用して不動産事業部門のみを切り出す場合、宅建業免許の取り扱いについて誤解が多く、注意が必要です。
たとえば、吸収分割によって宅建業を営む会社から別法人に事業が承継された場合、原則として新法人に対して新たに宅建業免許の取得が必要となります。これは、宅建業免許が法人単位で付与される「人格主義」であるためで、たとえ事業内容や従業員が同一であっても、法人格が変われば免許も別物と見なされるのが原則です。
このように、「会社分割」やその他の「組織再編」によって宅建業者の実体が変化する際には、単なる「代表者変更」や「役員変更」では済まない可能性があり、新免許の取得手続き、または変更届出だけで済むかの判断が非常に重要です。
組織再編を検討している段階で、宅建業免許の名義変更や新規取得が必要となるかどうかを事前に確認することが、トラブルや営業停止リスクを避けるカギとなります。
まとめ:事業譲渡と宅建免許、スムーズな引継ぎのために
事業譲渡における宅建業免許の取り扱いは、慎重な検討が必要です。譲受会社は、新規免許の取得手続きを確実に進めるとともに、顧客への丁寧な説明を心がけましょう。事業譲渡を成功させるためには、事前の準備と専門家への相談が不可欠です。株式会社〇〇や株式会社△△などの仲介業者を利用することも検討しましょう。
事業譲渡は、企業の成長戦略の一つとして有効な手段ですが、宅建業免許の取り扱いや顧客との関係など、注意すべき点がいくつかあります。これらの点を十分に理解し、適切な対応をとることで、スムーズな事業の引継ぎを実現することができます。事業譲渡を成功させるためには、綿密な計画と準備が不可欠です。また、専門家(弁護士、税理士、行政書士など)のサポートを受けることも有効です。事業譲渡は、企業にとって大きな転換期となるため、慎重に進める必要があります。
宅建業免許は会社ごとに個別に取得が必要な許可です。
たとえ事業内容をそっくり譲り受けたとしても、免許や保証協会の地位までは引き継げません。
そのため、事業譲渡を検討している企業は、以下の準備が必須です:
- 宅建免許の取得要件の確認と準備
- 譲渡スケジュールと免許取得スケジュールの整合性の確保
- 保証協会加入か営業保証金供託の選択
宅建業免許取得のご相談はお任せください
当事務所では、事業譲渡に伴う宅建業免許取得のサポートを数多く行っております。
法人設立・保証協会手続・免許申請まで、トータルサポートいたします。
お気軽にご相談ください。


